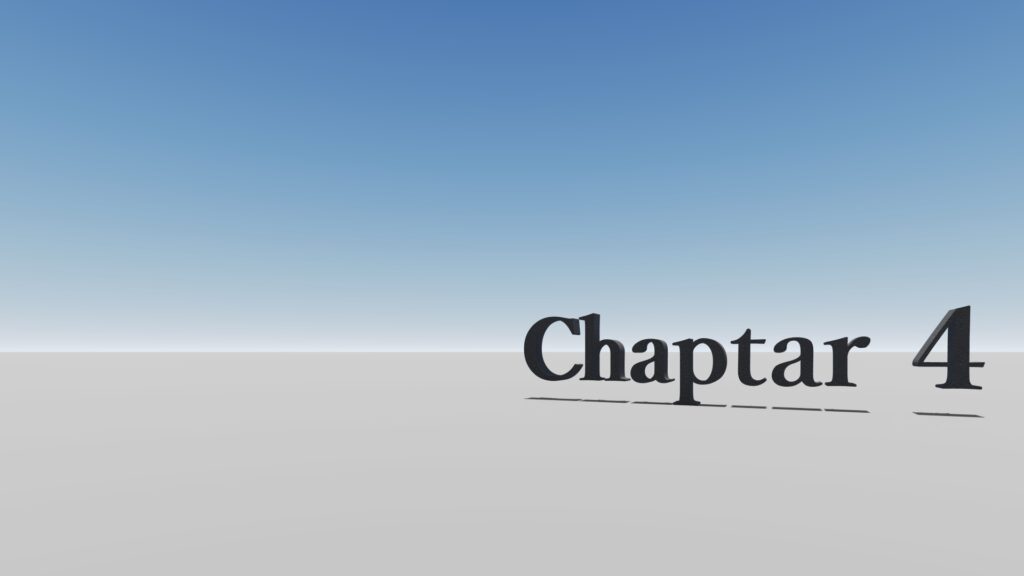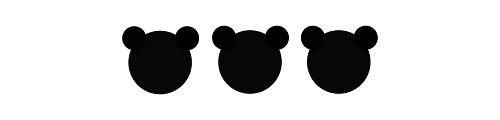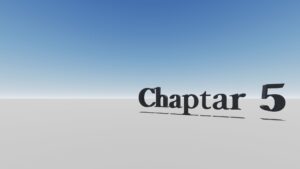第4章 「都市の多様性」に関する両者の比較
以上で見てきたように、ロバート・ヴェンチューリとジェイン・ジェイコブズはそれぞれ全く違う分野において別々の興味を持ち、それぞれ独特の生涯を送っている。しかしある一時期、1960〜1970年頃においてそれまでの近代主義を批判し、「都市の多様性」の重要さを論じたという点においてだけ両者は重なっている。
ここでは両者の生涯において位置づけられるそれぞれの考える「都市の多様性」についての思想を比較し、その共通概念と異なる概念を明らかにする。
まず、ロバート・ヴェンチューリはプリンストン大学で建築を社会学史、美術学史、古典的装飾様式から複合的に学び、首席で大学院を卒業した後、ローマの街を訪れその都市の多様性に感動する。そして美術史上で連綿と続く「多様な」建築への欲求の流れの中に位置づけられるモダニズム建築があることを認めた上で、それとは似つかず形骸化している「正統な現代建築家」によるモダニズム建築に反感を持ちそれを諧謔的に批判する。そのような流れの中で、都市については「多様性と対立性を備えた」要素が持つ「曖昧さ」によって「連想作用」が引き起こされ、それによって生じる都市の様々な見え方、変化していくイメージを良いと考えた。(第2章小結より)
次に、ジェイン・ジェイコブズはエリート主義を批判しており、高校を卒業した後、半年ほどで略記法を学び、すぐにジャーナリストの道に進んだ。ハドソン通りの街路の精査な観察と都市についての熟考により、都市の多様性とそれを生み出すための条件に気付く。また同時にモダニズム建築家たちの信じる思想がそれを破壊する根源となっていることにも気付き、それを真っ向から批判する。そのような流れの中で、都市について「たくさんの量、要素がある」ことは絶対的な必要条件で、そのたくさんある要素同士に「差」、「相違」が存在することによって都市における「変化」、「循環」、「連想作用」が引き起こされ、その「変化」、「循環」、「連想作用」のために都市は面白いものになると考えたことがわかった。(第3章小結より)
ここで、ヴェンチューリは、互いに対立するものを内に含んだ様々な要素を一貫して「多様性と対立性」という言葉で表現していることから、「多様性と対立性を備えた」要素は「内に対立性を含んだたくさんの要素」と言い換えられる。そしてこれはさらに「内に差・相違が存在するたくさんの要素」と言い換えられる。
よって、以上見てきたことにより、都市を多様性を持った魅力的なものにするために両者が共通して述べているのは
- 「たくさんの要素」が存在すること
- それぞれの要素のあいだに「差・相違」が存在すること
- その差・相違によって「連想作用」が引き起こされること
である。そして1の「「たくさんの要素」が存在すること」は多様である状態のことを言っており、「多様性」という言葉で言い換えられる。
都市についての両者の考えで共通していると言えることは、
「「たくさんの要素」が存在し、その要素同士のあいだに「差」、「相違」が存在することによって「連想作用」が引き起こされ都市は魅力的なものになる。」
である。これが両者が共通している「都市の多様性」の概念であり、現在曖昧である意味の最も重要である部分であると言える。
また、ヴェンチューリだけにあてはめることができる都市についての考えは、
「多様性と対立性を備えた要素」が存在し、その要素同士のあいだに「曖昧さ」が存在することによって「連想作用」が引き起こされ都市は魅力的なものになる。」
次にジェイコブズだけにあてはめることができる都市についての考えは、
「「たくさんの要素」が存在し、その要素同士のあいだに「差」、「相違」が存在することによって「変化」、「循環」、「連想作用」が引き起こされ都市は魅力的なものになる。」
二者の「都市の多様性」の思想にはずれがあり、二者に共通する意味を捉えようとすると、両者それぞれがその言葉により意味する概念より抜け落ちてしまう概念が存在し、その言葉の指す意味が少し漠然とした意味になってしまうことがわかった。二者の「都市の多様性」比較するだけで少しその意味が揺らいでしまうということは、「都市の多様性」について論じる人が増えれば増えるほど、それらの論者の中で共通する部分は少なくなって行き、その言葉が持つ一般的な意味はますます漠然としたものになっていくと考えられる。