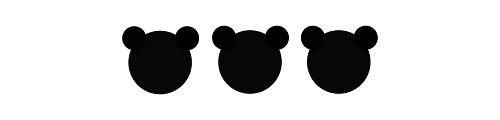第1章 序論

ガチ論文の「第1章 序論」です!
どういう背景、目的があって論文を書くか、みたいなことを書いてます!
第1節 研究概要
1-1-1 研究の背景
一般に、機能主義を命題とした近代建築はそれ以前の様式的な建築から決別を図り、20世紀中期において世界の至る所でモダニズム建築を生み出してきたとされる。しかし、機能主義の形骸化、硬直化に対する批判、歴史性や地域性の放棄に対する反省から、モダニズムを乗り越えようとする新しい動きが1960年代から1970年代に生まれる。それ以降、都市計画においてはそれまでの二者択一という考えではなく、両者共存の考えやブリコラージュの概念が広まり、建築や都市を論じる際に使われる言葉も徐々に変化し、「多様性」や「象徴性」、「大衆性」などの言葉が見られるようになる。
近代主義に相反する潮流として1961年、ジェイン・ジェイコブズが都市の多様性の魅力を前面に押し出し、アマチュアの立場から近代都市計画を真っ向から批判した『アメリカ大都市の死と生』[1]を出版し、1965年にはクリストファー・アレグザンダーがジェイコブズの考えと非常に近接した思想をシステムズ・アナリシスの立場から論理的に説明した[2]とされている『都市はツリーではない』を出版する。そして1966年、ロバート・ヴェンチューリが建築における歴史性を見直した『建築の多様性と対立性』[3]を出版する。
その後も上記のような書物に続き、建築・都市デザインに関する書籍が何冊も出版され、現在、都市計画やまちづくりに関する様々な論説や論文、書籍の中で、「多様性」という言葉が多用されすぎているように感じる。例えば、
“都市を訪れる魅力は、その多様性(diversity)にあるのではないか。(中略)都市の魅力はその多様性がもたらす変化に起因する”[4]
“都市は多様性をもたなければ、灰色一色で塗られたような淀んだ都市になってしまうだろう”[5]
などのように「多様性」という言葉は都市計画をする際、それさえあれば必ず魅力的な都市を創ることができる魔法の言葉であるかのごとく使われている。
1-1-2 研究の目的
本研究では、モダニズム建築家のもとで建築設計を学び、ポストモダニズムの建築家として非常に有名なロバート・ヴェンチューリとジャーナリストとして建築家を批判したジェイン・ジェイコブズが、対立する立場でありながらほぼ同時期に「都市の多様性」の重要性を論じたことに注目する。両者の生涯を通じて、通年的な視点で二人の人物を捉えると同時に、異なる人生の流れの中でそれぞれが重要であると考えた「都市の多様性」について明らかにし、その共通部分を示す。建築・都市の分野で非常に重要である二人の「都市の多様性」の共通部分は、現在意味が広がってしまっている「都市の多様性」の最も重要な部分であると言え、それを示すことで、「都市の多様性」の真髄を明らかにすることができると考えられる。
1-1-3 研究の位置づけ及び手法
ロバート・ヴェンチューリとジェイン・ジェイコブズはともに建築、都市の分野で非常に有名であるが、彼らの思想を通年的な視点で論じているものは少なく、ヴェンチューリに関しては日本語で出版されているものは見当たらない。そこで本研究では、ロバート・ヴェンチューリの生涯に関しては日本において訳本のない『Out of ordinary : Robert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』[6]を扱う。また、両者はともに1960〜1970年頃の思想が非常に有名であるが、それ以降の1980年頃以降における彼らの思想を扱ったものは少ない。本研究では上述の書籍『Out of ordinary : Robert Venturi, Denise Scott Brown and associates : architecture, urbanism, design』からヴェンチューリの後期(1978〜)における作品を通じてその時期における彼の思想を見る。また、ジェイン・ジェイコブズの著作で邦訳のない、『THE QUESTION OF SEPARATISM』(1981)を扱い、現在日本で公にされていない彼女の思想を明らかにする。また、ヴェンチューリとジェイコブズ二人の「都市の多様性」に関する思想を同時に比較している論は非常に少なく、妥当性のあるものは見当たらない。
[1]『THE DEATH AND LIFE OF GREAT AMERICAN CITIES』(邦訳:『アメリカ大都市の死と生』ジェイン ジェイコブズ著、山形浩生訳、鹿島出版会2010
[2]『建築の解体』磯崎新著、鹿島出版会、1997p.182
[3]『建築の多様性と対立性』ロバート・ヴェンチューリ著、伊藤公文訳、鹿島出版会1983
[4]『21世紀の都市を考える-社会的共通資本としての都市2』宇沢弘文、國則守生、内山勝久編、東京大学出版会、2003、p.163より引用。
[5]『都市の再生を考える1 都市とは何か』植田和弘他著、株式会社岩波書店2005より引用。
[6]David B. Brownlee, David G. De Long, and Kathryn B. Hiesinger著、PHILADELPHIA MUSEUM OFART IN ASSOCIATION WITH YALE UNIVERAITY PRESS 2001年
第2節 論文の構成
第1章「序論」では、本研究の背景を示し、本研究の目的を明らかにし、本研究の位置づけをすると同時に方法を定める。
第2章「ロバート・ヴェンチューリ」では建築家ロバート・ヴェンチューリを生涯通してみることでヴェンチューリが生涯でどのようなことから影響を受けたかを示し、彼の「都市の多様性」ついての思想を明らかにする。
第3章「ジェイン・ジェイコブズ」ではジャーナリストであるジェイン・ジェイコブズを生涯通してみることでこれまで語られてこなかった面を探るとともに、彼女の「都市の多様性」ついての思想を明らかにする。
第4章「「都市の多様性」についての両者の比較」では2章と3章で明らかになった両者の「都市の多様性」についての論を比較する。 第5章「結論」では両者の生涯を通じて「都市の多様性」を比較することで明らかになったことを述べる。
第3節 既往研究
■「ロバート・ヴェンチューリの作品研究—初期住宅作品の分析—」正会員 中沢健、正会員 小林克弘 日本建築学会梗概集(関東)1988年10月
ヴェンチューリの母の家について平面と立面の分析を行い、彼の作品の幾何学的な構成について分析したもの。初期の段階から後期芸術装飾品にみられるような幾何学的な設計をしていたことがわかった。
■「幾何学構成論Ⅳ ロバート・ヴェンチューリの作品研究2」正会員 中沢健、正会員 小林克弘 日本建築学会梗概集(九州)1989年10月
上記の論文の続きであり、リーヴ・ハウスとタッカー・ハウスの平面分析を行い、彼の設計手法における一貫性を明らかにすることを目的としたもの。
■雑誌『スペース・デザイン』1997年8月特集「R.ヴェンチューリ+D.スコット・ブラウン:90年代の作品」
ここではロバート・ヴェンチューリとデニス・スコット・ブラウンの90年代の作品を写真を中心にまとめてあり、90年代におけるロバート・ヴェンチューリの作品について理解するのに有用である。しかし、ここで芸術装飾品については取り上げられていない。
■雑誌『地域開発』2006年8月号において、「特集 J.ジェイコブズの都市思想と仕事」の中で9人の専門家によってさまざまな視点から論考が書かれており、ジェイコブズの全体像を理解する助けとなる。以下1つずつ挙げる。
「偶像的な偶像破壊者—J.ジェイコブズの都市思想といくつかの争点」矢作弘(大阪市立大学大学院創造都市研究科教授)
「アジアの都市とジェイコブズの思想」大西隆(東京大学先端科学技術研究センター教授)
「J.ジェイコブズの遺産—真のアーバニズムとは」ロバータ B. グラッツ(ジャーナリスト、都市評論家)
「J.ジェイコブズの都市思想の原点—都市の日々の暮らしへの視線」林泰義(まちづくりプランナー)
「J.ジェイコブズが教えてくれたもの」西村幸夫(東京大学大学院工学系研究科教授)
「J.ジェイコブズとマクロ経済学」中村達也(中央大学商学部教授)
「素顔のJ.ジェイコブズ素顔の現代日本」玉川英則(首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授)
「ジェイコブズと創造都市」佐々木雅幸(大阪市立大学大学院創造都市研究科教授)
「J.ジェイコブズと経済思想・経済理論」香西泰((社)日本経済研究センター特別研究顧問)
■細谷祐二「ジェイコブズの都市論—イノベーションは都市から生み出されるー」(雑誌『産業立地』2008年11月
都市とイノベーションの関係のメカニズムを浮き彫りにしたとして、『The Economy City』(1969)[1]の内容を、具体例をあげながら詳しく紹介し、現代の日本経済への教訓を引き出すことを目的とした論説。『The Economy City』の内容に入る前にジェイコブズの『The Economy City』執筆以前と以後について軽く触れられている。『The Economy City』のポイントを明快に整理した上で現在の経済学との関係、そして『The Economy City』にあげられた興味深い具体的な事例を紹介している。
[1]『都市の原理』ジェイン・ジェイコブズ著、中江利忠、加賀谷洋一訳、鹿島出版会、1971